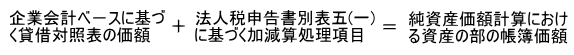純資産価額方式における勘定科目の処理ポイント(1)
株価計算の原則は「仮決算」
・株価の計算は、被相続人が亡くなった時点で「仮決算」をして計算するのが原則だが、「個別通達」において、直前期末の決算書の金額を基に計算することも認めている。
・仮決算にて株価を計算する場合には、「純資産価格方式のみ」によることとなり、「類似業種比準方式は採用できない。」
個別通達 (相続税、及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式、及び記載方法等について)の「第5表 1株当たりの純資産価額の計算明細書」の記載要領(4) ・株価の計算は、被相続人が亡くなった時点、すなわち課税時期において、「仮決算」を行うことが原則であるが、評価会社が仮決算を行っていないため、課税時期における資産、及び負債の金額が明確でない場合に、「直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるとき」は、課税時期における各資産、及び各負債の金額は、次の「イ」、「ロ」の金額を基に計算することも認められている。 |
イ.「相続税評価額」については、「直前期末の資産、及び負債を対象」とし、課税時期に適用されるべき相続税の評価基準を適用して計算した金額
ロ.「帳簿価額」については、「直前期末」の資産、及び負債の帳簿価額により計算した金額
|
「直前期末から課税時期までの間に資産、及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められる」における「著しい増減」とは ※「著しい増減」とは、例えば「土地等の売却」、又は「子会社を売却」した場合等により、直前期末から課税時期までの間に著しく資産、負債に増減が生じている場合をいう。 |
資産の部
| 勘 定 科 目 | 留 意 点 | |||
| 受取手形 | ・支払期限が課税時期から6カ月を超えるものについては、金融機関における割引回収可能額で評価する ・課税時期における回収不能額を控除して評価する。 |
|||
| 売掛金 | ・課税時期における回収不能額を控除して評価する。 | |||
| 未収入金 | ・課税時期における回収不能額を控除して評価する。 | |||
| 短期貸付金 | ・課税時期における既経過利息の額を元本価額に加算する。 ・課税時期における回収不能額を控除して評価する。 |
|||
| 商 品 | ・棚卸資産として、原則として下記により評価する。 販売価額−適正利潤−予定経費−消費税額 ・通常は、「帳簿価額と一致」する。、 |
|||
| 投資有価証券 (上場株式・上場投信) |
次の株価のうち最も低い株価で評価 課税時(亡くなった日)の終値 課税時(亡くなった日)の月の終値平均 課税時(亡くなった日)の前月の終値平均 課税時(亡くなった日)の前々月の終値平均
・相続税評価額iについて財産評価基本通達169〜172
|
|||
| 投資有価証券 (外国株) |
・外国株式の株価は、相続開始日の為替換算レートで邦貨(日本円)に換算する必要があります。 ・邦貨に換算するときの為替換算レートは、原則として、納税義務者(相続税を申告する人)が取引する金融機関が公表しているものを使用します。金融機関が公表する為替レートにはいくつか種類がありますが、相続税評価ではTTB(対顧客直物電信買相場)を使用します。
|
|||
| 投資有価証券 (公社債) |
・相続税評価額iについて財産評価基本通達197−2〜197−4 | |||
| 投資有価証券 (転換社債) |
・相続税評価額iについて財産評価基本通達197−5 | |||
| 投資有価証券 (貸付信託受益証券) |
・相続税評価額iについて財産評価基本通達198 元本 + 既経過収益 − 買取手数料 |
|||
| 投資有価証券 (証券投資信託受益証券) |
・相続税評価額iについて財産評価基本通達199 ・上場されているものは「上場株式に準じ」、その他のものは「解約請求による手取額」によって評価 ・「投資信託」については、投資信託協会で運営している「投資総合検索ライブラリ−」で探すことができる。 ・推移グラフの相続開始日にカ−ソルを合わせると、日付と基準価格が表示される。 |
|||
| 非上場株式 | ・取引相場のない株式として相続税評価額を算出する。 ・純資産価額方式による評価上は、評価差額に対する法人税相当額の控除(37%控除)は適用されない 。財産評価基本通達186−3 |
|||
| 非上場公募投信 | ・非上場の投資信託は、販売会社を通じて基準価額をもとに購入価額を算出して購入します。 基準価額はマーケット終了後に算出され、基本的には翌営業日の公表となるため、投資信託は冷静に運用できる。 ・死亡日の1口座当たり基準価格に保有口数を掛け、信託財産留保額や解約手数料を差し引く。 |
|||
| 売買目的有価証券 | ・法人税法上は「時価評価」が強制されるが、純資産価額方式による株式評価では「評価通達」により評価する。 | |||
| ゴルフ会員権 | ・相続税評価額は、財産評価基本通達211により評価する。 ・取引相場のある会員権の場合は、通常の取引価格の70%相当額で評価。 |
|||
| 仮 払 金 | ・旅費未精算など費用化されるものは、相続税評価額、帳簿価額のいずれからも控除する。 ・商品の買い付け等、棚卸資産として資産に計上すべきものは、そのまま資産として計上しておく。 |
|||
| 前 払 費 用 | ・「未経過保険料」、「前払家賃」などは財産性がないため、相続税評価額、帳簿価額のいずれもゼロとする。 ・仮払金と同じように考える。 |
|||
| 繰延税金資産 | ・税効果会計 を適用した場合の繰延税金資産は、相続税評価額、帳簿価額のいずれもゼロとする。 | |||
| 建 物 | ・帳簿価額は、減価償却累計額を控除したもの、 相続税評価額は固定資産税評価額に倍率(1.0)を乗じて評価する。財産評価基本通達89、93 ・課税時期3年以内に取得したものは、通常の取引価額(取得価額)とする。経過した分の減価償却費は、取得価額から控除してもよいとされている。財産評価基本通達185 |
|||
| 建物附属設備 | ・企業会計上、建物附属設備に区分したものであっても、建物の固定資産税評価額の計算対象となったものについては、建物の評価に準じて評価する。 ・通常は、「建物の固定資産評価額の中に含まれている」ので、評価はゼロである。 |
|||
| 機械装置 | ・一般動産として、原則として「売買実例価額」、「精通者意見価額等」により評価する。 ・圧縮記帳や特別償却を直接減額方式以外の方式(引当金方式、又は積立金方式)により行っている場合には、帳簿価額より減算する。 |
|||
| 土 地 | ・相続税評価額は、路線価方式または倍率方式等によって評価したものとする。
財産評価基本通達7 ・課税時期3年以内に取得したものは、通常の取引価額とする。財産評価基本通達185 |
|||
| 借 地 権 | ・帳簿価額については、有償取得のものは取得価額を、無償のものはゼロとする。相続税評価額は、借地権割合等を基に評価する。
・課税時期3年以内に 取得したものは、通常の取引価額とする。財産評価基本通達185 |
|||
| 「無償返還届書」を提出している場合の評価 | ・被相続人が同族関係者となっている同族会社が、「無償返還届出書」を提出して、相当地代を支払って被相続人所有の土地を借り受けている場合における同族会社の株式の評価上、純資産価額に算入する借地権の金額は、自用地としての価額の20%相当額で評価する。 | |||
| 偽の借地権 | ・民法の特別法である「借地借家法」により保護されることにより、個人の土地の20%評価減に伴う「見返り」としての「借地権20%相当額」を相続税評価額として計上する必要がある。
|
|||
| 評価会社が有する取引相場の無い株式 | ・評価会社が有する取引相場の無い株式を純資産価額方式により計算する場合には、評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除することはできない。(評価通達186−3(注)) | |||
| 借 家 権 | ・借家権については、権利金等の名称をもって取引される慣行のある地域にあるものについてのみ評価する。 建物の固定資産税評価額×1.0×借家権割合(30%) |
|||
| 保 証 料 | ・借入れの際の保証料については、繰上げ償還すれば現金として返ってくるので「資産性がある」と税務署は見ている。 | |||
| 電話加入権 | ・加入権1本当たりの標準価額に加入本数を乗じて評価する。 ・加入権の相場が下がっているので、帳簿価額に較べて評価金額がかなり低くなるケ−スが多い。 |
|||
| 未収保険料 | ・保険事故が発生している生命保険契約に係る保険金で、相続税評価額、帳簿価額とも同額を計上する。 | |||
| 保険積立金 | ・保険事故が発生しているものについては、 未収保険料として計上しており、すでに資産性はなくしているので相続税評価、帳簿価額とも計上しない。 | |||
| 保険積立金 | ・課税時期に保険事故が発生していない 生命保険契約で、支払い保険料が資産計上されていのものは、「生命保険契約に関する権利」として 個々の契約に係る解約返戻金相当額 により評価する。財産評価基通161 | |||
| 特許権 | ・権利者自らが特許発明した場合の特許権は、財産評価基本通達に定める「営業権の評価」として取り扱う。 ・特許取得に掛かった費用として帳簿価額を構成していても、評価としてはゼロとなるケ−スも多い。 |
|||
| 創立費・試験研究費 等の繰延資産 |
・「試験研究費等」の繰延資産は「財産性がない」ため、決算上の帳簿残高があっても、相続税評価額、帳簿価額ともゼロにする。 | |||
| 繰延税金資産 | ・将来の法人税等の支払を減額する効果を有し、法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格は有するが、税法上は還付請求できる性格のものではないため、相続評価額はゼロとする。 | |||
| 営業権・漁業権 | ・相続税は、営業上の権利についても課税対象としている。(相続税法10条1項13号、相続税基本通達10−6) ・財産評価通達は、企業の有する総資産の運用利回りを超える「超過収益力」を営業権として把握している。(財産評価基本通達165) ・営業権については、有償取得のものであるか、自家創設のものであるかを問わない。 ・評価上の営業権がゼロ円と計算された場合には、相続税評価額欄はゼロ円とし、帳簿額欄には帳簿価額を記載する。 |
|||
| 資産調整勘定 | ・非適格合併における合併法人が、被合併法人の資産負債を時価評価して受け入れる際の「時価純資産価額」と、その対価として時価純資産価額を超えて支払われる株式等の価額の合計額との差額を「資産調整勘定」として計上する。 ・「差額のれん」といわれるものであり、法人税法上の「営業権」ではない。 ・「営業権」であれば、減価償却資産として経済取引の対象となるが、「資産調整勘定」は、単なる「差額勘定」なので資産価値は無い。 従って、相続税評価額、帳簿価額ともゼロにする。 |
土地・建物の取得価額課税、 ・平成8年1月1日以降に開始した相続により取得した資産(土地等・建物等)については、旧措置法第69条の4の規定(いわゆる取得価額課税)が廃止されたことにより当該資産の評価はすべて財産評価基本通達の定めにより計算した金額(例えば、土地等については路線価方式又は倍率方式により計算した金額、建物等については倍率方式により計算した金額)により評価することとなるのか。
|