比準要素数1の会社の判定
第4表の考え方-「株価計算」と「判定」では用いる算式が異なる
・1株(50円)当たりの「年配当金額B」、及び1株(50円)当たりの「年利益金額C」の計算において、「株価算定」のためには、「直前期」と「直前々期」の平均を使用し、「比準要素1や0の会社判定」には、さらに「直前々期」と「直前々期の前期」の平均を使用する。
・つまり、株価計算においては、「直前期」と「直前々期」の平均の金額を「類似業種比準の計算」する際に用いる。
・「純資産金額」は常にプラスなので、「年利益金額」又は「年配当金額」のいずれかがプラスであれば「比準要素1や0の会社判定」とはならず、比準要素2の「一般の評価会社」として「類似業種比準の計算」が可能になる。 参照ペ-ジ
・配当・・・・・・・「直前期」と「直前々期」の「2年平均」を用いる。
・利益・・・・・・・「直前期」又は「2年平均」を用いる。
・純資産・・・・・・「直前期」を用いる。
比準要素数1の会社の判定
・比準要素数1の会社とは、直前期末を基とした類似業種比準価額計算上の評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」、「1株当たりの純資産価額」、このうち、いずれか「2要素がゼロ」であり、 かつ、「直前々期末においてもいずれか2要素以上がゼロ」である会社をいいます。
・類似業種比準価額の計算における比準3要素B、C、Dの計算に際しては、その計算過程において、次のような「端数処理」をする必要がある。
(B)1株当たりの配当金額・・・・・・・・・・・・・10銭未満の端数切捨て
(C)1株当たりの利益金額・・・・・・・・・・・・・円未満の端数切捨て
(D)1株あたりの純資産価額・・・・・・・・・・・・円未満の端数切捨て
| 事 例 1 |
| 配当金額 |
利益金額 |
純資産価額 |
||
直前期 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期 | 0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期の前期 | 0千円 |
400千円 |
(1,000千円)(注7) |
|
| 判 定 要 素 |
直前期末を基準 | (B1) (注1) |
(C1) (注3) |
(D1)(注5) |
| 0円00銭 | 0円 |
0円 | ||
0円 |
||||
| 直前々期末を基準 | (B2) (注2) |
(C2) (注4) |
(D2)(注6) |
|
| 0円00銭 | 0円 |
10円 | ||
2円 |
||||
・発行済み株式数は、1株50円換算で100,000株とする。
・直前期末を基とした判定要素(B1)、(C1)及び(D1)のいずれも0であるので、「比準要素数0の会社」に該当する。 ・比準要素0の会社は、課税時期に係る「直前期末の状況のみ」をもって判定対象にしているため、直前々期末の状況は一切問わない。 ・従って、「比準要素数1の会社」の判定は必要ない。
|
| 事 例 2 |
| 配当金額 |
利益金額 |
純資産価額 |
||
直前期 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期 | 0千円 |
1,000千円 |
0千円 |
|
| 直前々期の前期 | 0千円 |
0千円 |
1,000千円 |
|
| 判 定 要 素 |
直前期末を基準 | (B1) |
(C1) |
(D1) |
| 0円00銭 | 0円 |
0円 | ||
5円 |
||||
| 直前々期末を基準 | (B2) |
(C2) |
(D2) |
|
| 0円00銭 | 10円 |
0円 | ||
5円 |
||||
・直前期末を基とした判定要素(C1)が0ではない。直前期末以前2年間の実績による場合、下段5円になるので、「比準要素数0の会社」には該当しない。 ・直前期末を基とした判定要素(B1)及び(D1)が0であり、かつ、直前々期末を基とした判定要素(B2)及び(D2)が0なので、「比準要素数1の会社」に該当する。
|
| 事 例 3 |
| 配当金額 |
利益金額 |
純資産価額 |
||
直前期 |
0千円 |
0千円 |
10,000千円 |
|
| 直前々期 | 10千円 |
50千円 |
10,000千円 |
|
| 直前々期の前期 | 0千円 |
0千円 |
- |
|
| 判 定 要 素 |
直前期末を基準 | (B1) |
(C1) |
(D1) |
| 0円00(05)銭 | 0円 |
100円 | ||
0(0.25)円 |
||||
| 直前々期末を基準 | (B2) |
(C2) |
(D2) |
|
| 0円00(05)銭 | 0(0.5)円 |
100円 | ||
0(0.25)円 |
||||
・直前期末を基とした判定要素(D1)が0ではないので、「比準要素数0の会社」には該当しない。 ・直前期末を基とした判定要素(B1)及び(C1)が0であり、かつ、直前々期末を基とした判定要素(B2)及び(C2)が0なので、「比準要素数1の会社」に該当する。
|
| 事 例 4 |
| 配当金額 |
利益金額 |
純資産価額 |
||
直前期 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期 | 0千円 |
2,000千円 |
0千円 |
|
| 直前々期の前期 | 500千円 |
10,000千円 |
- |
|
| 判 定 要 素 |
直前期末を基準 | (B1) |
(C1) |
(D1) |
| 0円00銭 | 0円 |
0円 | ||
10円 |
||||
| 直前々期末を基準 | (B2) |
(C2) |
(D2) |
|
| 2円50銭 | 20円 |
0円 | ||
60円 |
||||
・直前期末を基とした判定要素(C1)が0ではない。直前期末以前2年間の実績による場合下段10円なので、「比準要素数0の会社」には該当しない。 ・直前期末を基とした判定要素(B1)及び(D1)が0ですが、かつ、直前々期末を基とした判定要素(B2)及び(C2)が0ではないので、「比準要素数1の会社」ではなく「比準要素数2の会社」になる。
|
| 事 例 5 |
| 配当金額 |
利益金額 |
純資産価額 |
||
直前期 |
500千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期 | 0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期の前期 | 500千円 |
1,000千円 |
- |
|
| 判 定 要 素 |
直前期末を基準 | (B1) |
(C1) |
(D1) |
| 2円50銭 | 0円 |
0円 | ||
0円 |
||||
| 直前々期末を基準 | (B2) |
(C2) |
(D2) |
|
| 2円50銭 | 0円 |
0円 | ||
5円 |
||||
・直前期末を基とした判定要素(B1)が0ではないので、「比準要素数0の会社」には該当しない。 ・直前期末を基とした判定要素(C1)及び(D1)が0ですが、直前々期末を基とした判定要素(B2)及び(C2)が0ではないので、「比準要素数1の会社」ではなく「比準要素数2の会社」に該当する。
|
比準要素数1の会社に関する取扱い
| 設 例 |
・比準要素である1株当たりの年利益金額を算出するに当たり、「C1の判定」ではプラスになるのだが、類似業種比準株価であるCの数値がマイナスになってしまう。
・整合性がとれないように思えるが問題ないのか。
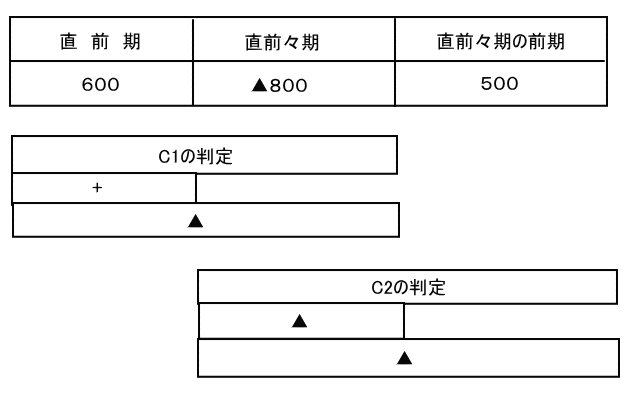
・「1株(50 円)当たりの年利益金額」の本番「(C) 」欄には、「直前期」である「ニの金額を⑤の株式数で除した金額」を記載します。 ・ただし、「納税義務者の選択により」、直前期末以前2年間における利益金額を基として計算した金額((ニ+ホ)÷2)を⑤の株式数で除した金額を(C) の金額とすることができます。 ・直前期のみで判定すれば「+」になるのだが、直前期末以前2年間における利益金額を基として計算した金額((ニ+ホ)÷2)を⑤の株式数で除した金額を(C) とすれば、金額類似業種比準株価である(C)はマイナスの数値になってしまい整合性がないが、問題はない。
|
相続税申告の対象会社に対する試算表
| 配当金額 |
利益金額 |
純資産価額 |
||
直前期 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期 | 0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 直前々期の前期 | 0千円 |
0千円 |
0千円 |
|
| 判 定 要 素 |
直前期末を基準 | (B1) |
(C1) |
(D1) |
| 0円00銭 | 0円 |
0円 | ||
0円 |
||||
| 直前々期末を基準 | (B2) |
(C2) |
(D2) |
|
| 0円00銭 | 0円 |
10円 | ||
0円 |
||||