遺留分とは
| 遺留分権利者 |
・「胎児」、「子の代襲相続人」も遺留分権利者に含まれる。
・一方、「相続欠格者」、「相続を廃除された者」、「相続を放棄した者」は、遺留分権利者にはなれない。
| 共同相続人 | 配偶者 | 配偶者以外 |
| 子と配偶者 | 4分の1 | 4分の1 (もし子供が2人の場合には8分の1ずつになる) |
| 父母(祖父母)と配偶者 | 3分の1 | 6分の1 |
| 配偶者のみ | 2分の1 | − |
| 子のみ | − | 2分の1 |
| 父母(祖父母)のみ | − | 3分の1 |
| 相 続 人 | 相続人全体の遺留分(総体的遺留分) | 相 続 人 | 相続人全体の遺留分(総体的遺留分) |
| 配偶者と子 | 2分の1 ※兄弟姉妹には 遺留分なし |
配偶者のみ・子のみ | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 直系尊属のみ | 3分の1 | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
・配偶者以外の相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて均等。 ・代襲相続人(孫以下)にも遺留分が認められる。
|
遺留分と特別受益
・生前に特定の相続人が財産の贈与を受けた場合、遺言書が無ければ「特別受益」として扱われるが、遺言書が存在すれば「遺留分の対象財産」に含まれる。
・「特別受益」は、計算には含めるが取戻しは不可能であり、被相続人による「持ち戻し免除」も可能である。
|
遺留分減殺請求権の効力
| 昭和57年3月4日最高裁判決 |
・遺留分減殺請求権は「形成権」であって、その行使により贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の権利で当然に遺留分権利者に帰属する。
・「形成権」とは、意思表示した時点でその効果が発生するものをいう。 |
遺留分の基礎となる被相続人の財産とは
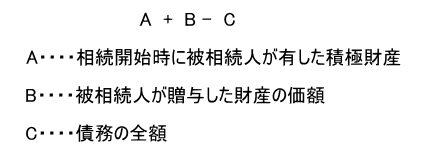
・上記算式のBの贈与については、「相続開始前の1年間にしたもの」に限り、その価額に算入する。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、 同様とする。 ・下記の最高裁判所判決により、実務では特別受益については時期、侵害の認識の有無にかかわらず全て加算して計算しており、「民法条文1030条は無視された状態」になっている。
|
| 事 例 1 |
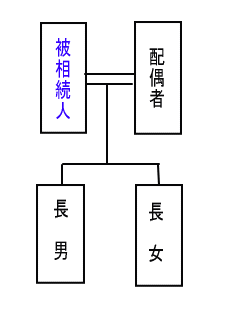
| 相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
| 配偶者 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
| 長 男 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
| 長 女 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
| 事 例 2 |
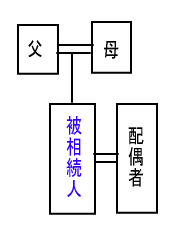
| 相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
| 配偶者 | 2/3 | 2/3×1/2=2/6 |
| 父 | 1/3×1/2=1/6 | 1/6×1/2=1/12 |
| 母 | 1/3×1/2=1/6 | 1/6×1/2=1/12 |
| 事 例 3 |
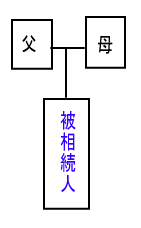
| 相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
| 父 | 1/2 | 1/2×1/3=1/6 |
| 母 | 1/2 | 1/2×1/3=1/6 |
| 事 例 4 |
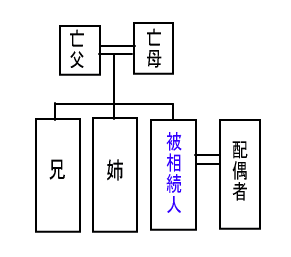
| 相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
| 配偶者 | 3/4 | 3/4×1/2=3/8 |
| 兄 | 1/4×1/2=1/8 | 1/8×0=0 |
| 姉 | 1/4×1/2=1/8 | 1/8×0=0 |
| 事 例 5 |
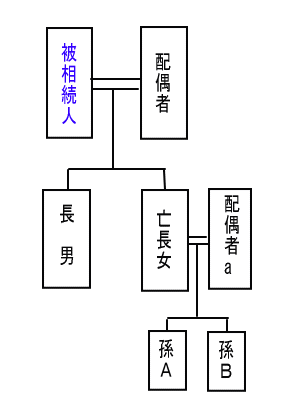
| 相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
| 配偶者 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
| 長 男 | 1/2×1/2=1/4 | 1/4×1/2=1/8 |
| 孫 A |
1/2×1/2×1/2=1/8 | 1/8×1/2=1/16 |
| 孫 B |
1/2×1/2×1/2=1/8 | 1/8×1/2=1/16 |
| 事 例 6 |
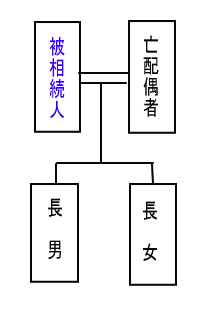
| 相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
| 長 男 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
| 長 女 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
| 事 例 7 |
・長男の配偶者、子供A、子供Bは、被相続人と養子縁組を結んでいる。
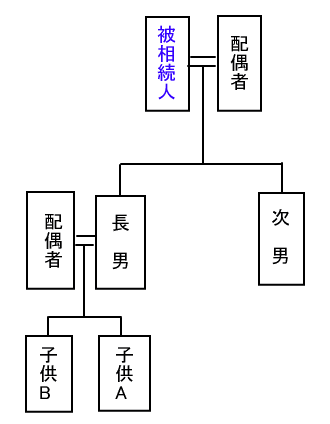
| 相続人 | 相 続 分 | 遺 留 分 |
| 配偶者 | 1/2 | 1/2×1/2=1/4 |
| 長 男 | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
| 次 男 | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
| 長男の配偶者 | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
| 長男の子A | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |
| 長男の子B | 1/2×1/5=1/10 | 1/10×1/2=1/20 |